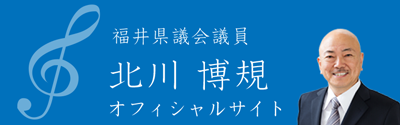2008年10月14日
俳句会の思い出 平成21年度 まつかぜ
私の父は、俳句を趣味にし、「沙羅詩」という俳号をもち、宮川史斗先生の主宰する「敦賀俳句会」に所属して活動していた。(晩年は敦賀玉藻俳句会で活動していたようである。)会員は十数名だったろうか、職場も同じ人が多いようであったが、人柄のよい方ばかりで、吟行にも時々ついていったのを覚えている。
その会では、俳句会が年に数回開催されていた。会員はその日までに作句し、十句ずつ持ち寄ることになっていた。自分が納得できる句を毎月10句創り上げるのは結構大変なことだったのだろう。夜、枕元の電気スタンドの下で、歳時記をめくり鉛筆を片手に句帳に書かれた自分の句を何度も何度も校正している父の姿から、父の頭の隅っこに絶えず「俳句」があったことが幼い私にも伝わってきたものである。
自分で納得できる句ができあがると、夕食の時などに、俳句のことなど何も分からない私たちに自分の句を披露し、自慢げに「何言うとるか(何を表現しているか)分かるか。」などと言ってきたりもしたものである。
さて、俳句会は、持ち回りで、メンバーの家を会場にして開催されていた。我が家の当番は大抵12月で、初旬の土曜日に忘年会を兼ねて行われていた。俳句会開催は我が家にとっては、法事と並ぶくらいの一大イベントで、開催日が決まると数日前から段取りに取り掛かる。当時は土曜日も午前中は仕事があったため、最終的に準備に許された時間は土曜の午後の数時間だけだったこともあり、姉と私も加わるのはあたりまえのことだった。
十数名とはいえ、我が家にその場をつくるのは大仕事だった。その作業は居間と奥の間の二間を仕切っているふすまを外すことから始まり、そこに居座っている家具を別の部屋へ移動させる。リフォームなどを経験した人なら分かると思うが、慣れてしまうと気づかないだけで、家の中にはなさそうでも結構いろんなものが置いてある。居間から他の部屋へ移動させるものだから、いたるところが物置場みたいな状態になった。
移動の際、特に問題になったのは父のもう一つの趣味でもあった骨董のたぐいであった。普段父が独占していた奥の間と呼ばれた床の間のある6畳の部屋には、所狭しと壺や陶器、そして古いことだけは確かな諸々のものが並んでいた。公務員だった父のことだから、高価なものなどは無かったのだろうが、(もちろん本人にとっての価値や思い入れは別のようだったが・・・)割れ物や重いものが多く、小学生だった姉と私にはとても神経を遣う作業だっのは言うまでもない。山積みにされた本も悩みの種だった。「ホトトギス」や「玉藻」といった俳句雑誌をはじめ、とにかく本に埋もれたようなエリアもあり、大仕事だった。
場所ができると、机運びである。近くのお寺から低い長机を6脚ほど借りて、運び入れるのだが、これが結構重く、父と二人で3往復。運び終わる頃には汗だくになった。
会は夕方4時頃から始まった。父たちの句会はおもしろかった。
ちょっと流れを紹介しておこう。
まず、締め切り時刻までに、メンバーが自分の創ってきた句の中から、これはと思われるものを10句清書して提出。それを別の人が一句ずつ細い紙に書き込む。
全員が書き終わると、幹事役(当番役)が全てを回収しよく混ぜて、それぞれの参加者に無作為に10枚(10句)ずつ配る。
それを受けとったら、各自が手にしている10枚の細紙の句を5句ずつ便せんに書き 写す。つまり、この時点で、誰の創った句なのか筆跡では判別できなくなるというわけだ。子ども心に「なるほど、うまく考えられているなぁ。」と納得したものだ。
ここまで済むと準備完了。
さあ句会スタート。いよいよ「選」である。ここからは、1時間ほど静寂の時間が流れる。お茶をすすりながら、たばこの煙の漂う中、整理番号のついた便せんがゆっくりと静かに会員の間を回されていく。
各自が、20枚ほどの紙に書かれた計100以上の句の中から、自分がよい句だと思 うものを10句書き留めていく。全員が、全ての句に目を通し、納得できる選ができた ら、各自が選んだものを別の紙に清書して提出。
さあ、ここからが佳境。いよいよ開票である。
幹事役が「○○選」と選者の名前を告げた後、その人が選んだ句を詠み上げていく。そ の度に誰彼となく、句についての高評が語られる。(自分の句が詠み上げられると、名のりを上げ、それを幹事が記録していく。)
全てのメンバーの選が詠み上げられたら、いよいよ集計して結果発表。
その日の一番多く指示された句、つまりその日の一等の句と、一番総合点の良かった人が発表される。
とまあ、こんな調子で句会はすすんでいったように記憶している。
さあ、ここからが母と私と姉の3人にとって一番大変な時間。
準備された簡単な料理と酒が出る。忘年会を兼ねていたこともあったのだろう、今の居酒屋程とはいかないが、普段とはちょっと違ったおいしそうな母の手作りの料理がテーブル毎に大皿に盛りつけられて運ばれる。ビールなんて出さない。とにかく日本酒である。飲みながら今日のそれぞれの句についての話があちこちで巻き起こる。酔ってくるとボルテージは上がっていき、笑い声が起こり、とにかく楽しい。みなさんが酒豪で、しかもほとんど何も食べずに飲む。日本酒を肴にして日本酒を飲むといった感じで、我々運び手は、酒が切れることのないように早め早めの手配に奔走する。大きな鍋の中に、熱燗の銚子が何本も並んでいる様は、なかなかの圧巻でもあった。姉と私の酒運び部隊は、その場しか居場所がないこともあって、真っ赤な顔をした父のそばで時々料理に手をつけながら、理解もできないいろんな人のやりとりを同じ空間で味わっていた。トロフィーや賞状があるわけではないが、何時間もかけて創った自分の句へのこだわりが認められたことが、なにものにも変えがたい酒の肴だったに違いない。
今のように、コピーとワープロが無い時代のこと、父が格闘した作句の跡は残っておらず、何冊かの句帳と自費出版した2冊の句集が残っているだけである。父が残した2冊の句集に目を通すと、あの頃の父の姿と、楽しそうに語り合う俳句会の様子が浮かんでくる。
あのときの子ども心に感じたうらやましさは何だったのだろう。趣味に生き、同じ志を持った者と酒を酌み交わし、語り合う、そこにはそれぞれのもつ感性や人間味があふれていたそんな仲間に囲まれていた父の姿なのだろう。
自分は俳句をたしなむような粋な部分はもっていないが、俳句会の思い出は、2冊の句集と共に私の宝ものである。大事にしていきたい。